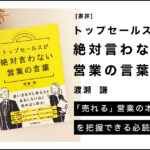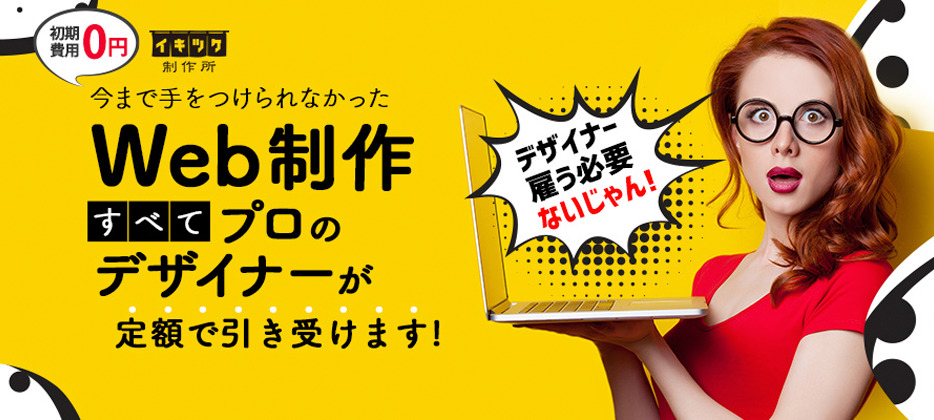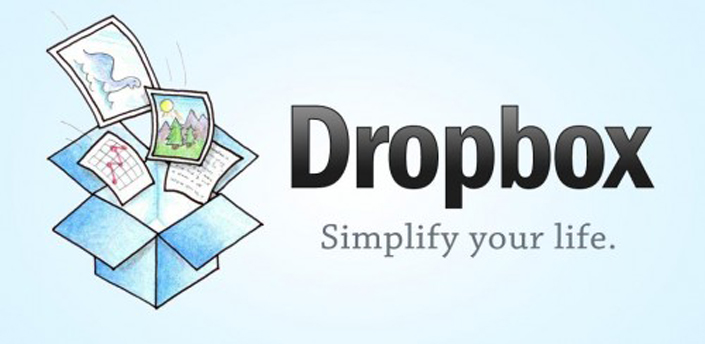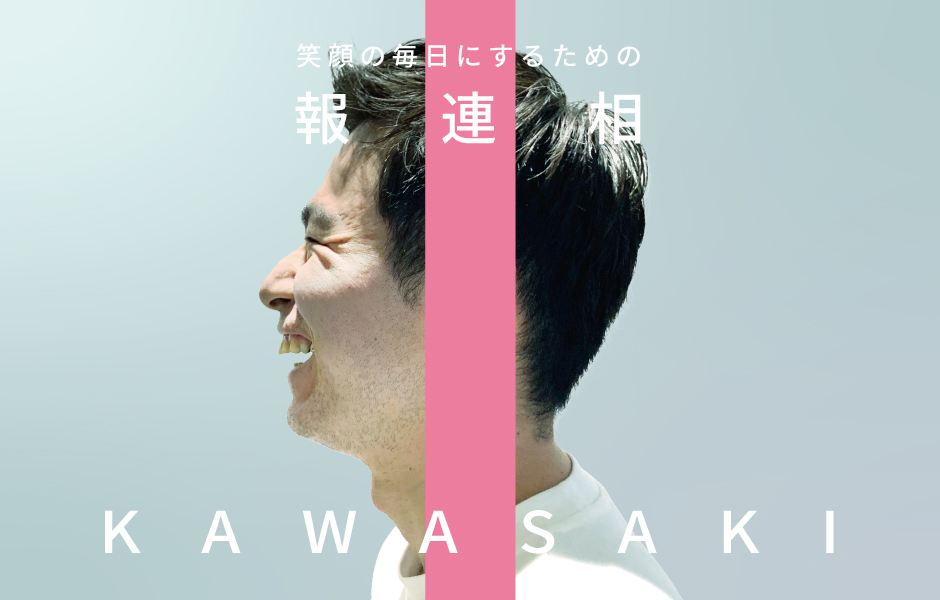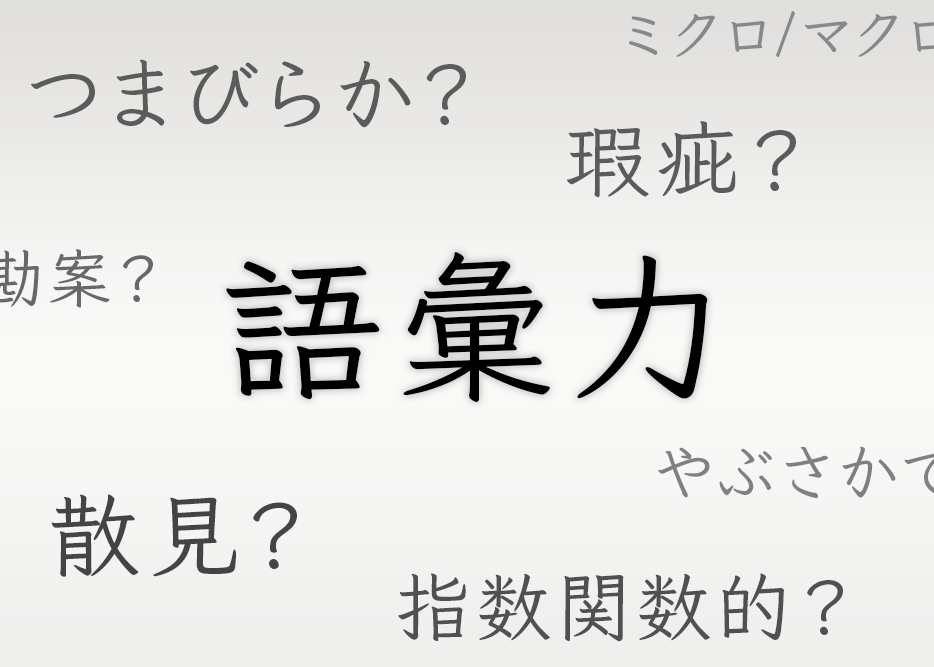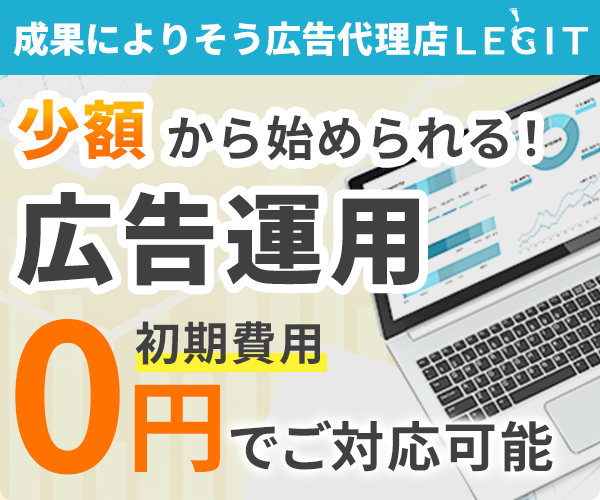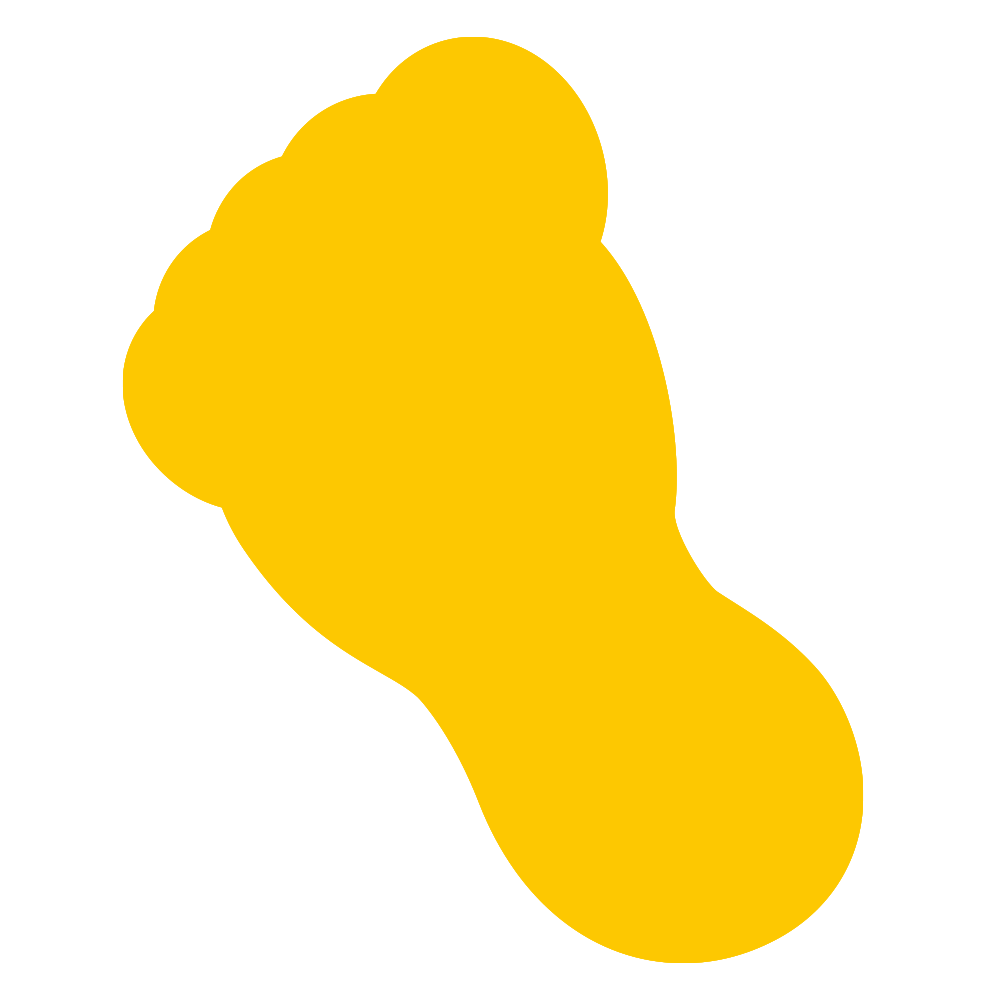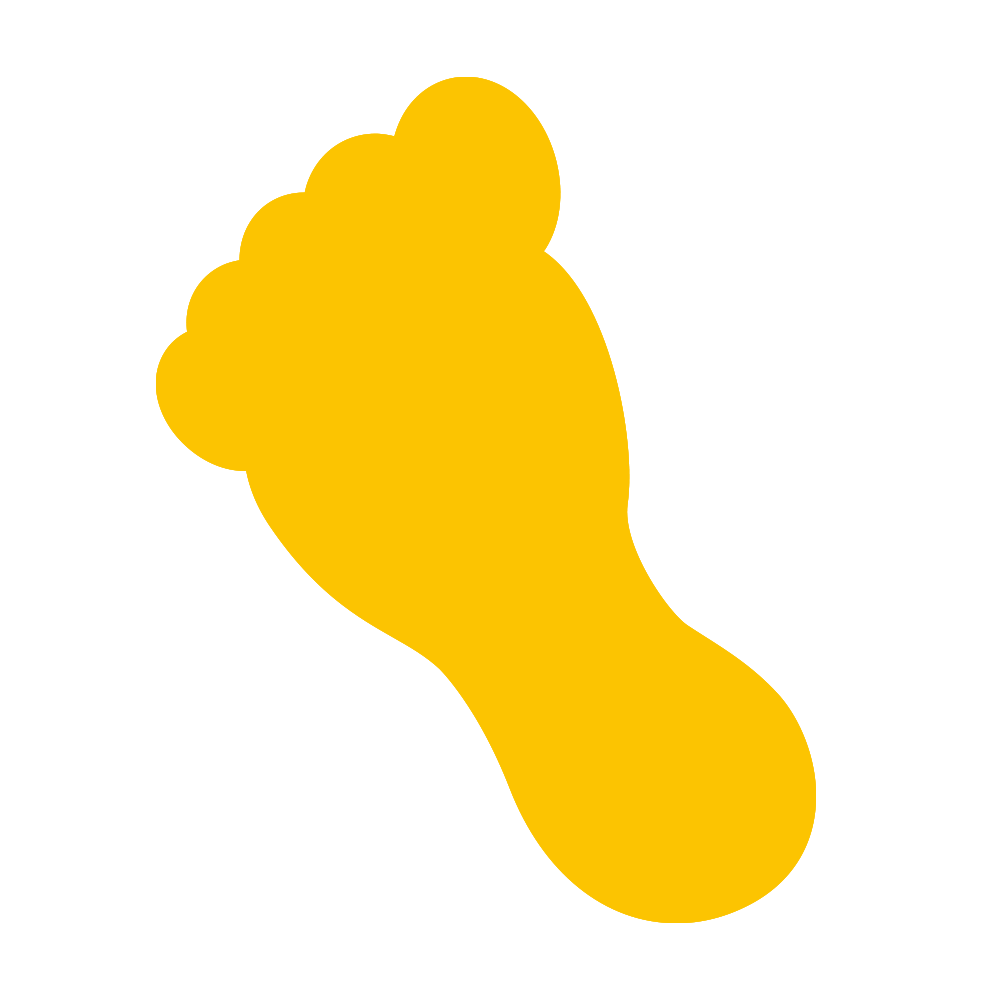こんにちは。
デザイナーとして入社した3ヶ月後、なぜかサブスクモデルの脱毛サロンを運営することになっていた旅田です。
いまは事業部から離れていますが、当時からは店舗もスタッフも増え、それに伴い組織体制やメニュー内容もどんどん変容しながらここまで歩んできています。
気がつけば男性専門脱毛サロン剛毛クラッシュはオープンから一周年が過ぎ、女性のエステ・脱毛サロンジークラもコロナに負けじと売上を伸ばしています。
これらの脱毛サロンで特に人気なのが『フェイシャルエステ通い放題コース 月額7,980円(税抜) 〜』のサブスクメニューです。

これがめちゃくちゃ気持ちいい。
お客さまからは「とっても気持ちがいい」「お肌の調子がよくなった」などといったお声も多く上がり、本当に大人気のサービスとなっています。
また、こうした成功事例を日々目の当たりにしていると、サブスクこそが真にWin-Winで持続可能なビジネスモデルだと再認識させられます。
今回は、そんなサブスクというビジネスモデルについてご紹介していきます。
こちらを読み進めていただくことで、サブスクサービスを利用してみたい方や、サブスクモデルでより高い価値を提供していきたい事業者の方など、双方にとっての理解が深まれば幸いです。
※なお、本記事では私が実際にサブスク事業の運営体験を通して得た知識やノウハウを中心に語りますので、一般的な説明とは異なる場合がある点、あらかじめご了承ください。一旦、わかりやすく言い切らせていただきます。
サブスクとは

サブスク(=サブスクリプション)型モデルとは、登録さえしておけば継続して何度でもサービスが受け続けられるモデルのことです。
サブスクを直訳すると「定期購読」ですから、新聞や雑誌同様、契約を交わすことで対価となるサービス(≠モノ)を定期的に享受できる仕組みとも換言できます。
あえて「≠モノ」と表現しましたが、その通りで、サブスクの真髄は「モノ」ではなく「コト」にフォーカスしている点だと私は考えています。
サブスク=コト消費
そもそも「サブスク」と呼ばれるモデルが流行りだす以前から、似たような概念として「定期購入」がありました。
これはその名の通り、定期的に何かを購入する(させる)モデルを指していますが、本来購入とはモノを得る行為を指していました。
ところが、オンライン技術の進歩によってモノやコトの価値が変容していきました。
YouTubeにアクセスすれば、分厚い図鑑にしか載っていなかった珍しい昆虫を動画で見ることができます。
SNSで繋がっていれば、遠く離れた国の友人とも気軽にコミュニケーションがとれるようになりました。
いわゆる「モノ消費」から「コト消費」の社会に変容してきたというお話ですが、サブスクはこうした世の中の変化によって生まれた新しいモデルといえるでしょう。
定期購入との違い
定期購入とサブスクとの違いは「モノ消費」「コト消費」の対比構造とまったく同じで、物質的なモノを得るための対価を払うことと、何かしらの体験ゴトに価値を見出して対価を払うこととの違いと捉えることができます。
ちなみに、サブスクには「何度でも」「無制限に」といったニュアンスが含まれているような錯覚に陥りがちですが、語源となる「subscription」には本来そういった意味は含まれていません。
この錯覚も「コト消費」の観点に立つとうまく説明できます。
すなわち、モノは使うと消耗したり消滅したりしますが、コトにはそういった劣化現象がないため、どうせ一定の金額なら何度でも体感しようという意識が働くからではないでしょうか。
簡単にまとめると次のようになります。
- 【定期購入】の目的 =定期的にモノを得ること(モノ消費)
- 【サブスク】の目的 =定期的にコトを得ること(コト消費)
サブスクの特徴

サブスクがひとつのビジネスモデルとして注目されているのは、ここまで述べてきたモノやコトに対する価値観の変容に加え、サービスはどれだけ顧客目線であり続けられるかといった考えが作用しているのではないでしょうか。
それは、単に良い製品(モノ)を届けることが目的ではなく、それを使うことで得られる喜びや感動体験(コト)をコンテンツとしたサービスになっているかどうか、と言い換えられるかもしれません。
そしてサブスクには、この「コト」にどれだけ重きを置けているかといった “度合い” があると考えています。
“度合い” がある
メディア論で有名な英文学者のマーシャル・マクルーハンは、メディア論におけるコンテンツの説明として「メディアの中のメディアに当たるものである。そのため、コンテンツはメディアでもある。」と述べたそうです。
果たしてコンテンツとは「製品」なのか、それともその製品(=メディア)を使うことで得られる「体験」なのか。
サブスクがサブスクたらしめるのは、「体験」をより意識したサービスにできているかどうか、といった点にあるのではないでしょうか。
結論、サブスクには物質的な「モノ」とその対極にある非物質的な「コト」のどちらにどの程度の重きを置かれているか、という度合いがあると考えています。
度合いの異なるサブスクの具体例は次章で紹介します。
最後に、サブスクのメリットとデメリットを簡単にご紹介します。
(本当はそれぞれについて詳しく紹介したいところですが、とても語りつくせないので割愛させていただきます。)
メリット/顧客側
- 初期費用がかからない
- 使い放題である場合が多い
- 無料期間がある場合が多い
- 定額のため購入しやすい
- 契約の手間がほとんどない
- いつでも解約できる
- モノに依存しにくい(場所を取らない)
デメリット/顧客側
- 利用頻度によっては都度払いよりも高くつく
- 不必要なサービスまで含まれる場合がある
- 利用していなくても料金を支払う場合が多い
メリット/事業者側
- 顧客と継続的な繋がりを得られる
- 顧客情報を集めやすい(サービス品質を向上しやすい)
- 収支計画が立てやすい
- 新規ユーザーを獲得しやすい
- お試しプランを導入しやすい
- 業種や業界に囚われない
- モノに依存しにくい(在庫リスクが低い)
デメリット/事業者側
- 顧客満足度をあげないと解約される
- 解約が多いと収支計画が立てにくくなる
- 導入のためのプラットフォーム利用料が発生する
- 自動支払いの機能に問題があると膨大な手間がかかる
- 常時サービス提供の体制を敷く必要がある
サブスクの具体例

ここまでサブスクを私なりに解説してきましたが、ここから具体的な例も紹介していきます。
身近な例ということで、我が家で契約している「利用し放題」のサービスを洗い出したところ、以下のようなラインナップとなりました。
- YouTube Premium /月額1,550円
- Apple TV+ /1年間のお試し期間中
- Apple Music /月額980円
- flier /月額500円
- Amazon prime /年額4,900円
- Amazon 定期おトク便(Amazon prime内のサービス)
- Netflix /月額1,200円
- フィットネスクラブ /月額15,555円
こうして上げてみると「そんなに登録してない方だな」と思っていても、意外と多い感じがします。
総額およそ2万円強… 結構家計を圧迫してるなぁと思う一方、そのほとんどがフィットネスクラブなので、それを思うとサブスクって本当に安価でコストパフォーマンスがいいと感じています。
これらのサービスについて、前章でご紹介した「サブスク度合い」を軸にカテゴライズしていきます。
いわゆるサブスク
- YouTube Premium
- Apple TV
- Apple Music
- filer
- Amazon prime
- Netflix
サブスク度合いが非常に高い、いわゆるサブスクと呼ぶにふさわしいサービスです。
これらはすべてコンテンツの利用権を提供する形式であり、モノにも依存しないため、そういった意味でもサブスクの代表格とも言えるでしょう。
ただしfiler(本の要約が読めるサービス)は、プランによっては読める冊数に限りがあるため、無制限に使い放題という訳ではないです。
とはいえ、バリバリ「コト消費」的なサービスなので、ここでいうサブスクの定義はバッチリ満たします。
不完全なサブスク
- Amazon 定期おトク便
- フィットネスクラブ
これらのサービスは、サブスク度合いの低さゆえにサブスクと呼ぶには不完全であると考えられます。
Amazon 定期おトク便
定期おトク便は、そもそもAmazon primeを契約しているユーザーに対して「定期的に注文してくれたら10%OFFするよ」といったサービスです。
定期購入できる商品は限られますが、リストにはいつでも追加・削除できますし、手数料なども発生しません。
しかしモノ消費の面が強いため、サブスクと呼ぶには不完全であるといえます。
フィットネスクラブ
こちらはサブスクという言葉が流行る前から存在していた、いわゆる月額会員制のクラブになります。
月額費用さえ支払えば施設が使い放題という意味では問題なさそうですが、次の点でサブスクと呼ぶには不完全だといえます。
- 入会手数料がかかる場合が多い
- 施設の営業時間外には使えない
- 設備を共有するため使えないタイミングがある
施設や設備といった物理的に存在するモノに依存するサービスのため、同じ定額料金を支払っても体験して得られる価値に差がある場合が出てしまいます。
脱毛サロンは?
では、冒頭で紹介した『フェイシャルエステ通い放題コース 月額7,980円(税抜) 〜』はどうでしょう?
結論、こちらも不完全なサブスク寄りになってしまうでしょう。
こちらもサロンの予約状況によっては利用できない可能性があるためです。
ただ、必ず念頭に置いておきたいのは、サブスク事業のポイントはどれだけ顧客目線であり続けられるか、です。
確かに、事実として剛毛クラッシュやジークラは予約ができない時間帯もあるでしょうが、このサロンに関わる従業員は全員が「お客さまが身も心も美しくなるために全力でお手伝いする」ことにコミットしています。
例えば、エステティシャンは休みの日程や時間帯を被らないように調整しながら、常に予約が埋まらないような努力を怠っていません。
フェイシャルエステのために足繁く通っていただくお客さまに対しても、妥協せず、常に120%の施術ができるように心掛けています。
だから、決して安くない月額料金でも喜んで契約し続けてくれますし、何度も足を運んでくれます。
サブスクたらしめるもの
言ってしまえば、上記の脱毛サロンでは「綺麗になった顔」というモノではなく、「綺麗になれたことで満足感いっぱいになる」というコトをお客さまに体験してもらうことに重きを置いています。
これはフィットネスクラブでも同じで、「スリムになった体」というモノではなく、「スリムになったことで自分に自信が持てる」というコトが重要になります。
サブスクがサブスクたらしめるのは、「体験」をより意識したサービスにできているかどうか、でしたよね。
イキツケ制作所
弊社では、デザイン制作の定額制サービス『イキツケ制作所』を運営していますが、こちらもサブスクと言えます。
こちらは月額5万円でデザイン制作やウェブサイト構築といった技術的なお手伝いをするサービスです。
こちらもまた、納品物をモノとして捉えると難しいですが、あくまでこの納品を通してお客さまの課題を解決するという体験を提供しています。
実際にはデザインやコーディンング業務だけでなく様々な業務を請け負っている場合も多いので、ご興味あればぜひ一度お問い合わせください。
『イキツケ制作所』フォーム:https://www.legit.co.jp/ikitsuke
あとがき
今回、様々なブログを拝見しつつ自分の考えをまとめていきましたが、意外にもサブスクの定義は曖昧な部分も多かったです。
一年前、脱毛サロンを運営するとなったときから「定期購入」との違いについてはアレコレ考えてはいましたが、今回の記事でそれを一部だけでも言語化できたのがよかったです。
「サブスクについて詳しく聞いてみたい」という事業者の方も、ご興味あればぜひお問い合わせください。
-
Prev
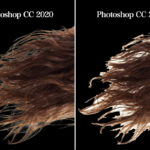
Photoshop CC 2020年6月の最新アップデートで髪の毛など複雑な被写体でも1クリックで選択可能に!
-
Next
書評「トップセールスが絶対言わない営業の言葉」NGワードで営業の本質を学ぶ